更新日:2024年10月31日
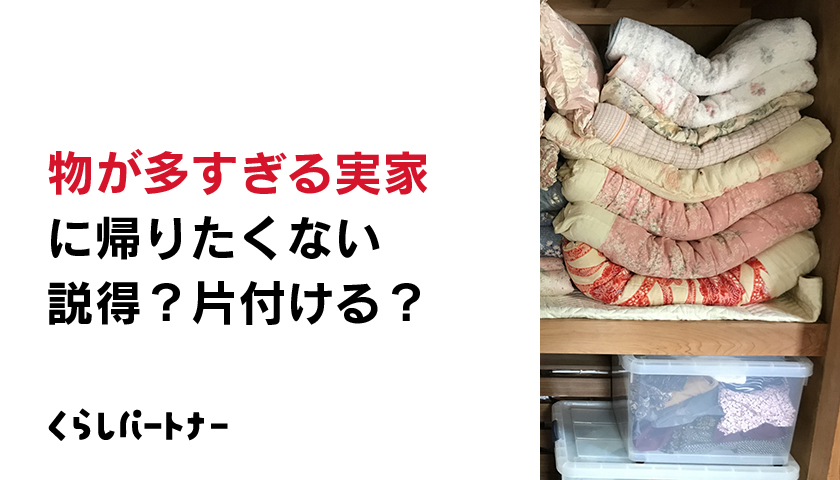
親元を離れ、久しぶりに実家に帰ってみると物が溢れているということはありませんか?
親に片付けるようにいっても全く聞く耳をもたないので、イライラしてしまったり、実家に帰るのが億劫になるなど、悩んでいる方も少なくありません。
そこで今回は、片付けたがらない親を説得する方法や片付けを進めるコツについてまとめました。

帰省をして、物が多く生活感が溢れた実家を見ると、ついイライラしてしまったり、もう帰りたくないなぁと悩んでしまう方もいますよね。
など、片付ける気が全くない親を見るとさらにストレスに…ということも。
そもそも、なぜ親は物を捨てたがらないのか?
親側の気持ちを理解することで、今よりもうまく話し合いが出来たり、説得ができるかもしれません。
60〜80歳代の親たちは、戦後間もない貧しい時期や高度経済成長期を体験してきた世代。親世代が生きてきた時代は、モノを持つことは”豊かさ”を象徴する時代でもありました。
「まだ使えるものを捨てるのは、バチがあたる」「捨てるのはもったいない」という考えから、”とりあえず取っておく”ということが習慣になり、物が増えてしまっている傾向があります。
高齢の夫婦二人暮らしなのに、布団や食器類がやたらに多いということはありませんか?それは「来客がある時のためにとっておきたい」「何かの時に使えそう」などと思うためです。
実際には大人数が来客する機会は滅多になく、子ども側からすると要らないものなのですが、本人たちはいつか使う大切なものと考えているのです。
記念品のガラスの置物、働いていた時の名刺、子どもの工作など、長年生きてきたからこそ、思い出の物が増えていきます。
思い出の物が捨てられない人の多くは、物を捨てることで大切な思い出まで消えてしまう気がして、手元に取っておくことがあります。
子ども世代は、ミニマリズムのように、不要な物を持たないという考えを持つ人も多くいます。ですが、親たちにとって物が多い暮らしは当たり前のこと。むしろ物があることで安心感を得ている場合すらあります。
親は「別に今の暮らしに困っていない」「なぜ片付けなければいけないのか?」と思うので、片付けをめぐって意見が食い違ったり、喧嘩になったりしてしまうのです。

親から「私が死んだら片付けて」と言われたり、「何度言っても片付けないので、もう放っておこう」と思うこともありますよね。ですが、実家の片付けを先送りにするのは避けたほうがよいでしょう。
日本の平均寿命からみても、まだまだこの生活が続いていき、今よりも悪化する恐れもあります。また、子ども側も歳をとっていくので、いざその時が来ても自力で片付けるのが難しくなります。
他にも、以下のようなリスクが考えられます。
ですので、できるだけ早めに、コツコツと片付けを進めておくことが重要になります。

実家の片付けをうまく進めるためには、親自身が片付けに対して前向きな気持ちになることです。
そのために行うべき声掛けや、親を説得するためのポイントを以下にまとめました。
まずは親が片付けをしたいのかどうか、しっかりと気持ちを確認しましょう。
子ども本位で片付けを進めてしまうと、片付けをめぐって親と喧嘩になってしまうこともあります。
しっかりと話を聞くことで「実は物が多くてこんなことに困ってた」「捨て方がわからなくて悩んでた」など、親の悩みも出てくるかもしれませんよ。
親が気力や体力、判断力があるうちは、一緒に片付けができるので、手間や負担を軽減できます。
また、歳を重ねると新しい環境やチャレンジすることにどうしても億劫になってしまいます。親が元気なうちのほうが、子ども側の意見も聞いてもらいやすく、片付けでの言い争いも起こりにくくなります。
もしも、つぎのような項目が増えたときは、片付けが必要なサインです。
親の健康状態によっては、すぐにでも片付けやサポートが必要なこともありますので、日頃から様子をよく見ておきましょう。
「何度言っても片付ける気がない」というときは、生活の変化が起こったタイミングに声掛けをすると聞き入れてもらいやすくなります。
など、特別な来客がある時、ご自身の健康や生活に実際に影響が出た時は、片付けの必要性を感じてもらいやすくなりますよ。
自分の親だからこそ「なんで片付けないの!?」「こんなもの使わないでしょ!」と言いたくなる気持ちもわかります。ですが、親を責ためり、否定する言い方はNGです。
まずは現状のリスクや困っていること、親が心配であることを素直に伝えましょう。
など、できるかぎり前向きな声掛けで片付けの必要性やメリットを伝えるようにしましょう。
捨てるのに罪悪感を感じてしまったり「もったいないから捨てられない」というタイプの親には寄付やリサイクル、買取を提案するのがおすすめです。
捨てるのではなく、「売ってみようか」「欲しい人に譲ろうか」と提案することで、親の価値観を否定することなく、ものを手放すことができます。
たとえ実家であっても、あくまで親が住んでいる家であることを忘れてはいけません。
片付けが進まないからと言って、勝手に物を捨てるなどの行為はNGです。また急かしてしまうことで、親の機嫌を損ねてしまうこともあります。
あくまで親が主導で片付けを進め、力仕事といった作業面を子どもが手伝うというやり方がおすすめです。

親が前向きに、かつ抵抗なく片付けられるために、まずは普段の生活スペース(リビングや寝室)から遠い場所から片付けるのがおすすめです。
順番は以下の通りです。

子ども部屋にあるのは基本的に子どもの物。親としても片付けを受け入れやすい場所です。
「子どもの物を無断で捨てるわけにもいかない…」と実は親が悩んでいることもあるので、親孝行の一環として一番に取り組みましょう。
子ども部屋がスッキリするとお互い達成感が得られ、片付けに前向きな気持ちになれますよ。

生活スペースからもっとも離れているので、片付け作業がしやすい場所です。多すぎる傘や履いていない靴を捨てたり、床に置いたままになっているものを収納するだけでも、かなりスッキリしますよ。
玄関が片付くと家の出入りがしやすくなるので、親に片付けると暮らしやすくなるという良さを感じてもらいやすいです。

廊下や階段に物が置いたままになっていると、歩きにくいですし、転倒の恐れもあります。
基本的には廊下や階段には、荷物を置かないようにしましょう。廊下や階段がキレイになると、片付けの動線確保ができます。今後の片付けのことを考え、早めに取り組みましょう。

使っていない植木鉢、自転車、物干し竿など、重たくて運べない、捨て方が分からないという理由から外に放置されている場合があります。捨て方を調べる、運搬するなどのサポートをしてあげましょう。
また、庭が荒れている様子が見られれば、雑草を抜いたり、雑草が生えないよう対策をしてあげるのもおすすめです。

狭いスペースでありながらも毎日使う大切な場所。ですがよく見ると、使っていない掃除道具、旅先で持ち帰ったアメニティ、贈答品でもらったタオルなどで、実はまったく使っていないものが隠れています。
また高い戸棚に洗剤などの買い置きを収納すると、気づかずに無駄に買い足してしまうこともあります。なるべく届きやすい場所、普段から見える場所に収納するなど、親が物を管理しやすくなる工夫も大切です。

台所は収納場所も多いので、親が片付けにかなり前向きになった時に取り掛かるのがおススメです。
親が台所にこだわりを持っている場合は、賞味期限切れを捨てる、2個あるやかんを1つだけ捨てる、お皿は今住んでいる人数分だけ残すなど、納得しやすい理由があるものから処分するといいですよ。
また吊り棚など高い場所には、もう使っていない台所用品が隠されているので、そこから取り掛かるのもよいでしょう。
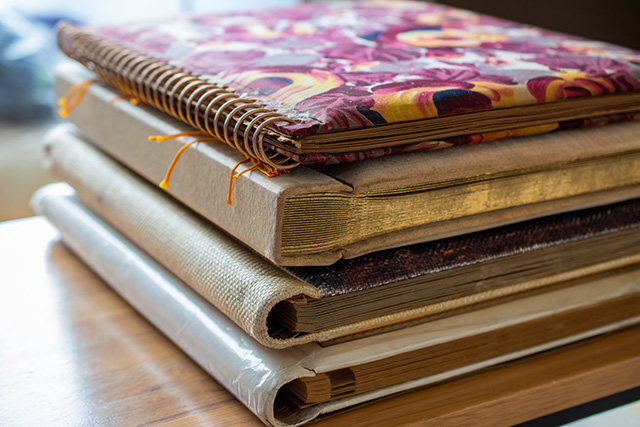
思い出の品や趣味の物は判断にどうしても時間がかかるので、後回しで大丈夫です。あまり無理に片付けを進めると、親が物のない寂しさから、もとに戻してしまうこともあります。
全て綺麗に片付けることが目標ではなく、まずは「床に物が落ちていない」「廊下や階段が通りやすい」など、親が安心・安全に暮らせる状態を目標に取り組んでみてください。

もし、片付けても定期的にゴミを溜め込んでしまう、実家がゴミ屋敷のようになっているという時は、第三者に協力を仰いだり、専門業者に依頼するのがよいでしょう。
片付け専門の業者などであれば、短期間で不用品の撤去から清掃まで行ってくれます。また業者によっては、立ち合いなしでの作業を引き受けてくれるので、頼れる兄弟や親戚がいない時にもおすすめです。
また親の健康状態によっては、行政や福祉と連携した対応が必要なケースもあります。ご家族だけで悩まず、専門機関に相談をしましょう。
「実家が汚い」「物が多い」などの理由で、帰りたくないという人は少なくありません。親が歳をとると、そういった悩みも増えていきます。ぜひお悩みの方は、今回ご紹介した方法を試してみてください。