更新日:2024年11月14日
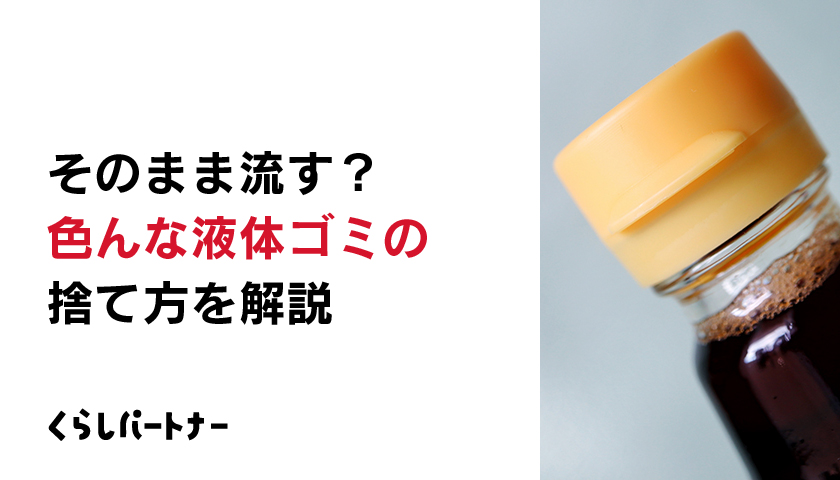
賞味期限切れの調味料、使い終わった古い油といった”液体のゴミ”の捨て方に迷うことはありませんか?
液体ゴミを捨てるとき「いつもモヤモヤしてしまう」「調べてもイマイチ分からない」という方に向け、今回は身の周りにあるさまざまな液体の正しい処分方法についてご紹介します。

液体が入ったままゴミとして捨ててしまうと、以下のような危険があります。
さまざまな自治体で液体ゴミを出す際の注意を呼び掛けています。できるだけ中身を使い切ってから捨てるか、容器を空にしてからゴミに出すようにしましょう。

いらなくなった液体は「普段洗い物をするキッチンシンクに流せば大丈夫」と思う方もいるかもしれません。ですが、キッチンシンクに何でも流して良いわけではありません。
家庭から排出される水は、すべて水道管を通り、処理場で適切に処理されてから川や海に放流されます。トイレやお風呂など、家のどこで流しても行き着く先は同じです。
排水口に流してはいけないものを流してしまうと、臭いや汚れが発生し、設備の故障や設備の寿命を縮める原因となります。それだけでなく、環境にも悪影響を及ぼす可能性があるので、正しい処理方法を守りましょう。
それでは、迷ってしまいがちな液体の処理方法についてそれぞれ詳しく解説していきます。

醤油やみりん、ドレッシングなどの調味料は、塩分濃度が高いため、そのまま流すと水質汚染につながります。そのためシンクなどに流して捨てるのはNGです。
調理後の煮汁や、余った刺身醤油なども同じです。少量であっても洗う前に、一度ふき取るなどすると良いでしょう。

ケチャップやマヨネーズといった粘度が高いものを流すと、環境への悪影響や詰りの原因になります。
その他にもジャムやソース類など、粘りがある調味料はこの方法で捨てることができますよ。

サラダ油・オリーブオイル・ごま油など種類に限らず、油を流して捨てるのはやめましょう。
環境への影響はもちろん、油は冷えると固まる性質があります。流してしまうと配水管に付着したまま残り、さらに後から流れてくるものがくっついてしまい、配水管の詰まりの原因となります。
他にも油凝固剤や油吸収パッドを活用したり、食用廃油の回収などを利用して処分ができます。調理後のフライパンなどについた油も、キッチンペーパーなどでふき取ってから洗うようにしましょう。

容器の中身が液体・固形に関わらず、捨てる時は中身を出して処分しましょう。レトルト食品は、固形物や油分が含まれるため、当然流して捨てるのはNGです。
賞味期限がかなり過ぎている場合は、中身が腐敗している危険もあります。賞味期限切れのレトルト食品を開封する際は、床に新聞紙を敷くなどの飛散防止対策や換気を十分にしてください。

ジュース・コーヒー・お茶などの飲料水は、コップに残った程度であれば、そのまま水に薄めながらシンクに流して問題ありません。ビールや日本酒といったお酒も同様です。
ただし、ジュースやお酒などの飲料水にはアルコールや糖分などの有機物が多く含まれているため、一度に大量に流すと水質汚染の恐れがあります。
大量に捨てたい飲み物があるときは、流さず捨てるのがよいでしょう。

洗濯用洗剤・食器用洗剤・掃除用洗剤といった液体洗剤は、少量であれば、水で薄めながら流せば問題ありません。ただし大量になる場合は、新聞紙などに染み込ませて処分するのが理想的です。
注意すべきなのは、塩素系洗剤です。塩素系洗剤は酸性洗剤と混ざると有毒なガスが発生します。また、原液のまま流すと配水管が痛む恐れもあります。
液体洗剤を処分するときは、必ず一種類ずつ、それぞれ分けて処分しましょう。

毎日使っている程度のシャンプー・コンディショナーを流して捨てるのは問題はありません。ただし、大量の原液をそのまま流して捨てるのはやめましょう。粘り気がある液体なので髪や汚れと絡まり、詰りの原因になります。

アルコール消毒液は、揮発性があり引火しやすい物質です。そのまま流すと配水管の中で火災が起きる危険があるので、絶対にやめましょう。
ジェル状の消毒液も同様の手順になります。作業をする際は危険ですので、火の気がなく、十分に換気できる場所で行ってください。

目薬やお子様が風邪をひいた時に処方されるシロップ薬など、医薬品などの化学物質は、環境や生物にとって有毒な成分も少なくありません。そのため市販薬であっても薬は、燃えるゴミとして処分するのが望ましいです。
栄養ドリンクも同様で、特殊な成分が含まれているためそのまま流して捨てるのはやめましょう。もしわからないことがあれば、薬局などに直接相談することもできますよ。

マニュキュアは水に溶けない物質のため、そのまま流してしまうと詰りの原因になります。きちんと処理をして処分をしましょう。
中身の液体が固まっている場合は、除光液を使って固まった部分を溶かすといいですよ。

香水の主成分はアルコールなので、発揮性が高く引火の恐れがあります。また油分も含まれているため、そのまま流すと配管に臭いが染みついてしまいます。
アルコール消毒液などと同様、火の気がなく、風通しの良い場所で作業を行いましょう。

除湿剤の容器にたまった液体は、塩化カルシウムの水溶液です。中身はそのまま捨てることができるので、水に流しながら流しましょう。
成分が残るとサビの原因になるので、残らないようにしっかりと水で流すようにしてください。
ゼリー状になったものも、そのままゴミとして捨てることができますよ。ただし、肌に刺激を与えることがあるので、捨てる際は手袋などを使うようにしましょう。
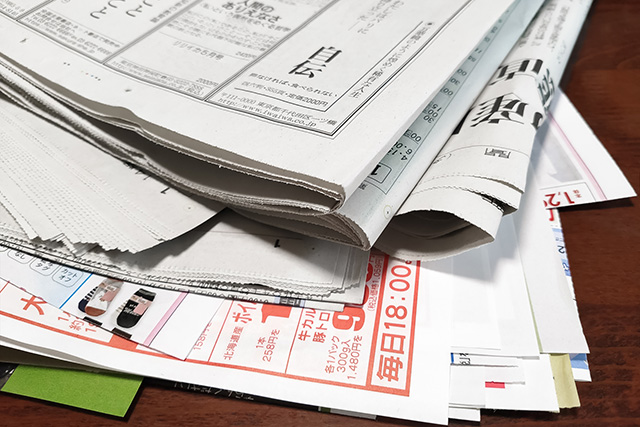
ご紹介してきたように液体ゴミは、紙や古布などに染み込ませ、漏れ出ないようビニール袋などに入れ処分するというのが基本になります。
液体ゴミを捨てたいときは次のアイテムがあると便利です。どれも簡単に手に入るので、日頃からストックしておくのがおすすめです。
よく揚げ物調理をする方には、定番の油凝固剤をストックしておくのもおすすめです。100円ショップ・スーパー・ネットで手軽に手に入りますし、調理後に溶かすだけでよいので、他のアイテムを用意する必要がないのも嬉しいポイントです。
吸水ポリマーとは、水分を吸収するとゼリー状に固まる合成樹脂のこと。おむつや保冷剤などに用いられ、単体でネット購入できます。少量で多くの水を吸収し、漏れ出る心配もなく、液体処理に便利です。災害時での簡易トイレや、キャンプで残り汁処理など活躍するシーンも多く、あると便利なアイテムの一つです。
今回は、さまざまな液体の捨て方についてご紹介しました。普段何気なく流して捨てているものの中にも、流してはいけないものがあるかもしれません。ぜひお住いの自治体の処分方法をチェックしてみてくださいね。
自治体の公式情報や公開データをもとに、家庭で迷わず正しく処理できるよう、わかりやすく整理しました。ゴミ捨てのルールは自治体ごとに異なります。最新情報はお住いの自治体の公式サイトなどでご確認ください。